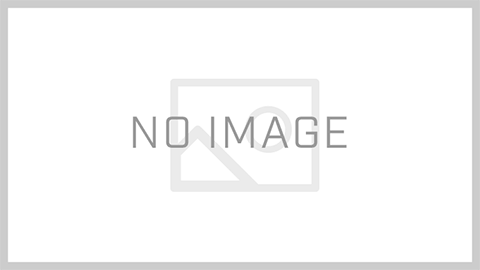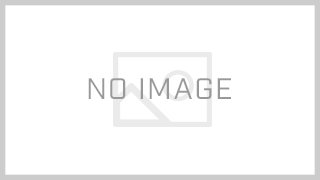日清食品が2014年に出した「カレーメシ」
当時手軽に食べられるカレーといえば「レトルト」で白米を別に用意するのは当たり前だった
水を入れてレンジにかけるだけでカレーライスになるという商品は強い疑いさえあった
しかし実際に味覚調査をしてみると味の評判はすこぶる良かった
黄色い米のぬいぐるみが暴れまくる奇天烈なCMで印象つけることでカレーメシは大ヒット
2022年度シリーズの売り上げは100億円を突破した。
バーモンドカレーは安定しているものの売り上げが年々減少していた。
夫婦共働きで子供のいない若年夫婦世代を狙った開発が必要だった。
そこで作ったのがバーモンドカレーシェフズアレンジ
カレールーからペーストに変えたことで調理に40分かかったカレーが10分でできる
ハウス食品は徹底的にリサーチしてからこれを出した。
- ロイヤルユーザーからの収益を伸ばす
- 通常のユーザーをロイヤルユーザー化して収益を伸ばす
- 自社プロダクトを認知している潜在顧客を新規顧客化して収益を伸ばす
- 自社プロダクトを認知していない潜在顧客から認知を獲得し、一気に新規顧客化して収益を伸ばす
- 離反・休眠状態にあるユーザーを元に戻して収益を伸ばす
成功企業は仮説をたてた定量・定性調査を愚直にやっている
- 月980円の有料に入っている
- 3ヶ月で500万インプレッション以上ある
- 500人以上のフォロワー
Goolgleのクッキー受け入れ停止リターゲティング広告
ユーザーがブラウザでウェブを見る
サーバーが「ここに来ました」って返すのがクッキー←禁止
このユーザーが別のサイトにアクセスするとクッキーで情報を見てるからピンポイントで広告を打てる←このリターゲティングも禁止
顧客データはファーストパーティーだけが持つことになる
アップル、グーグル、マイクロソフト、メタ、LINEやYahoo
コンテキストマッチング
ウェブサイトの内容をAIが分析して内容に合った広告をオークションして貼り付ける
クッキーで個人データを見ることを禁止されたのなら気Jの方を軸にして記事に相応しい広告を入れる
ユーザーが自発的かつ意図的に企業に提供する個人データのことを指します。これは、企業がユーザーの行動を追跡したり、推測したりして得るのではなく、ユーザー自身が「これを知ってほしい」と思って提供する情報です。
配偶者のいないシングルで年収1000万円以上に限定すると全体の0.7%
アプリマーケティング
第1フェーズ
商品カタログの電子化
商品やブランド名を冠したカジュアルゲーム
第2フェーズ
事業と密接なアプリが増え始める(無印のアプリ)
会員証をデジタル化
バーコードをレジで表示すると購入金額に応じたポイントが貯まる
顧客IDに紐づく購買データを実店舗経由で収集できるようにした
第3フェーズ
単なるチャンネルではなく、商品サービスの利用や購買などのCXにアプリを組み込むことで価値を大幅に増幅させる(日本コカ・コーラのアプリ「Coke ON」)
日本コカ・コーラは自動販売機と連動したアプリ「Coke ON」の開発で自動販売機のCXを大きく変えた
- 商品を買う時、ポイントを貯めれば好きなドリンクを1本もらえる
- 歩いてもポイントを貯められる
- サブスクで月3300円で1日2本まで交換できる
- 現金を入れて買った商品のお釣りを電子マネーでもらえる
- クレカはもちろん銀行から直接アプリにチャージできる独自の電子マネー
これによって日本コカ・コーラはさまざまな顧客データを得られるようになった。
クラシコム
北欧雑貨のECサイトはアプリ経由の売り上げが65%
ウェブやSNSに分散していたコンテンツをアプリに集中させることでCXを向上させた
仏壇のはせがわ
ダウンロード23万人
会員登録は21万人
顧客の売り上げが年間6億円超え
店舗での接客で「供養に関してわからないことが多いのに相談できる相手がいない」という問い合わせが頻繁にあった
そこで、故人の命日を登録してもらうようにした。
命日に連動して情報配信
法事の時期をプッシュ通知でリマインド
ブランドというものは企業のものじゃなくて顧客のもの
日々商品を使っていくことで「これはいいクレンジングだなあとか」愛着が増していく
そうして頭の中にブランドが形作られていく
ネーミングやパッケージロゴや広告などは顧客の頭の中にあるブランドを連想しやすくする手段でしかない
ファンケルは青いボトルが象徴的だったがよりスタイリッシュにする目的で白に変えた。
顧客は青い瓶を探すので見つからなくなってしまって売り上げ不振に陥った
ロングセラーブランドを多く抱える日清は定番のヌードルの味は変えずにパッケージや素材を時代に合わせて変化させている
ラ王のように名前は浸透していても味が時代に合わないと感じればレトルトの生麺からノンフライ麺への大改革もやってみる
ローソンは2020年、PB商品のデザインを一斉に変えて同じデザインに統一した。
棚に並ぶとどれがどれだか分からないと炎上
新規顧客が入ってきたことで売り上げは減らなかったが、既存顧客が逃げてしまうことを危惧してものすごい速さでパッケージを作り直した。
結果男女の割合がほぼ半々になり、売り上げも順調に伸びた。
じゃあどのブランドは変えるべきでどのブランドは残すべきか
顧客を5つのセグメントに分類して管理する「5segs」
例えば「未認知顧客」「認知・未購買顧客」から「一般顧客」へと段階を進めたい場合
マーケティングの課題はブランドの存在が知られていない、商品の価値、便益、独自性が伝わっていない
「一般顧客」から「ロイヤル顧客」へ進めたい場合はリピート購入につながっていない、競合に比べてブランド名が想起されない
「離反顧客」から「一般、ロイヤル顧客」へ復帰を狙う場合、想起率が下がり顧客は自然に離反しているケースが多い
識別記号とはロゴやパッケージやキャラクター
- ユーザー像
- 商品カテゴリ
- 人格イメージ
不二家の場合はロゴが古臭くて子供っぽいという課題があったのでリブランディングに踏み切って成功した
広告を作る側はすぐにロゴやパッケージを変えちゃおうと考えるけど、それは余程のことがないとうまくいかない
セブンの商品広告、リテールメディアは2年で売り上げが10倍
85%はメーカーの販促、セブンが狙ってるのは販促以外のマーケティング
テレビやスマホの広告と違うのは買ってくれた購買データが結びつけられるから
ダイレクトで広告の効果が分かる